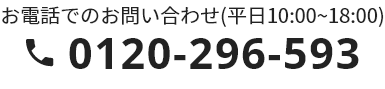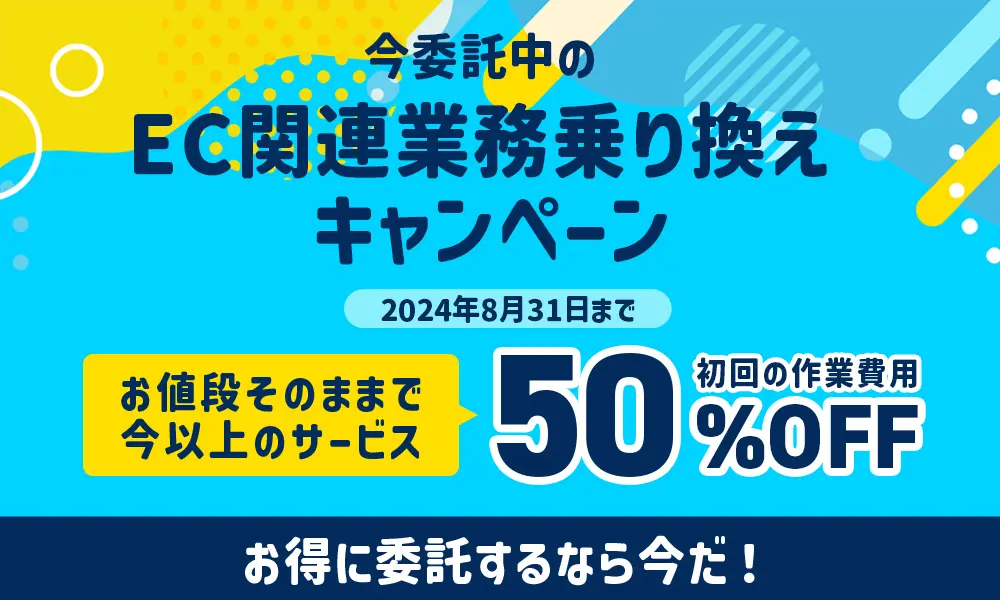DAGMAR理論とは
DAGMAR理論(ダグマー理論)とは、
1961年にR.H.Colley氏が各広告主の実態調査を基に発表した、
広告の目標達成度合いを数値で評価する、広告の効果測定方法、モデルのこと。
広告の世界では古典的な理論ではありますが、
今でも広告管理のあり方を考える重要な理論として位置づけられています。
このDAGMAR理論では、消費者の購買に至るまでのプロセスを
「コミュニケーション・スペクトラム」と呼ばれる、
5段階の認知レベルに分けて、説いています。
DAGMARとは?
Defining Adverting Goals for Measured Advertising Results
の頭文字を取ったものです。
D=Defining(定義すること)
A=Adverting(広告の)
G=Goals for(目的)
M=Measured(測られる)
A=Advertising(広告の)
R=Results(結果)
つまり、「広告効果を計測するために、広告の目的を定義すること」です。
コミュニケーション・スペクトラムとは?
上述したように、
DAGMAR理論では消費者の購買に至るまでのプロセスを
5段階の認知レベルに分けて考えています。
各項目は以下の5つです。
未知(unawareness)
消費者が商品・サービスを全く知らない状態
知名(awareness)
消費者が商品・サービスを認知している状態
理解(comprehension)
消費者が商品・サービスを理解している状態
確信・トライアル(conviction)
消費者が商品・サービスを購入しようか検討している状態
行動・レギュラー(action)
消費者が商品・サービスを購入した状態
広告を実際に配信する前に、自社の商品・サービスの
「知名率」「認知率」「理解率」「確信率」「行動率」の5つを調査し、
この調査結果を基に5段階それぞれに目標値を設定します。
広告配信後に再度各項目の調査を行い、
前後で比較して目標値に対する達成度合いを見ながら
広告効果を測定するのが「DAGMAR理論」です。
DAGMAR理論のメリット
DAGMAR理論のメリットは、
広告配信における各プロセスごとの成功・失敗を
把握することができる点です。
仮に広告が直接売上に繋がっていなかったとしても、
広告の効果・問題点をより詳しく考えることができます。
例えば、
・未知⇒知名に至る数が少ない
広告が消費者に届いていない可能性があり、
もっと広告を目立たせる必要があります。
・理解⇒確信に至る数が少ない
商品・サービスに消費者が好意的でない可能性があります。
このように、各プロセスでの消費者数がわかれば、
広告の問題点、そして対処法について検討しやすくなるのです。
また、知名⇒トライアルにどれだけ繋がっているのかを見れば
コンバージョンレートがわかったり、
トライアル⇒レギュラーにどれだけ移行しているのかを見れば
リテンションレートを把握することができます。
上記のように各項目同士を比較検討することで、
フローの流れを滞らせている要因を探ることも可能です。